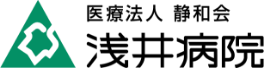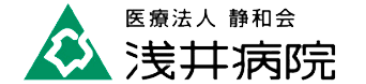広報誌「はんてん木」
浅井ヘルスケア グループ内の出来事をまとめた広報誌です。
「第五回浅井リハビリテーションレクチャー」を開催しました

10月31日金曜日18時より、A棟5階大会議室において「第五回浅井リハビリテーションレクチャー 転倒予防の昨日、今日、明日」を開催し、内外から50名の方々にご参集頂きました。
講師には、亀田総合病院から村永信吾リハビリテーション事業管理部部長をお招きし、講演「チーバくんも足元からはじめる安房発ロコモ対策」を賜りました。座長には、浅井ヘルスケアグループの大切なパートナーである城西国際大学から福祉総合学部 竹内弥彦教授にお越し頂きました。
村永先生は、日本整形外科学会が提唱しているロコモティブ症候群啓発の中心メンバ―であり、全国に広まっているロコモ度テスト(立ち上がりテスト・2ステップテスト)の開発責任者です。ロコモ度テストは、TVの情報番組や雑誌でも度々紹介されており、浅井ヘルスケア グループでも、はんてん木祭りや東金市産業祭などでロコモチェックコーナーを行ったこともあるので、ご記憶にある方もおられるかと思います。「ロコモ」とは、骨・関節・筋肉などの運動器が障害され、立つ・歩くといった移動機能の低下を来した状態を言いますが、ロコモ判定結果と転倒との因果関係、ロコモ度テストを活用した運動指導、効率的な栄養補給、幅広い世代を支える地域での取り組みなど、転倒予防について、臨床家、研究者、教育者の視点からご高話頂きました。
今回のレクチャーでは、講演の前に、当科の理学療法士が、10月に群馬県高崎市で開催された「日本転倒予防学会第12回学術集会参加報告」を、また、転倒転落小防止委員会委員の立場から「浅井病院における転倒予防活動」を発表しました。
前者では、転倒予防における他医療機関の先駆的事例、転倒予防対策・被害軽減グッズを報告し、入院時や転倒後の理想的な流れをまとめました。後者では、令和6年度インシデント・アクシデントレポートから転倒事例を抽出し、データを事故防止に2次活用できるよう、病棟毎に転倒場所・頻発時間帯の特徴をまとめました。
転倒によって大腿骨頸部骨折や脊椎骨折などが生じると、活動が制限されて、生活の質や幸福度の低下を招いてしまいます。村永先生から頂戴した様々な示唆とこれらの情報を活かしながら、リハビリは多職種連携を忘れず転倒予防活動に貢献したいと思います。